32歳営業マンがスキマ時間で検証したリアル。管理人のやまとです。
はじめに
営業として数字と成果に向き合う毎日の中で
副業も「数字で確かめたい」という思いが強くなりました。
「レンディングで預けるだけで増える」といった案件を見るたびに
甘い言葉ほど裏を見たくなる性格です。
今回は、仮想通貨レンディング型サービス IZA KA-YA を
公開情報をもとに“預けて増える説”を冷静にチェックしてみました。
結論:預けるだけで増えるのは条件次第
IZAKA-YA は、理論上
「仮想通貨を貸して、運用利益から利回りを配る」構造を掲げています。
ただし、運用の中身・リスクの所在・透明性が曖昧であり
「預けるだけで安心して増える」とは言い切れません。
利回りを得る可能性と、失う可能性の両方を理解したうえで扱うべき案件です。
サービス内容と表示利回り
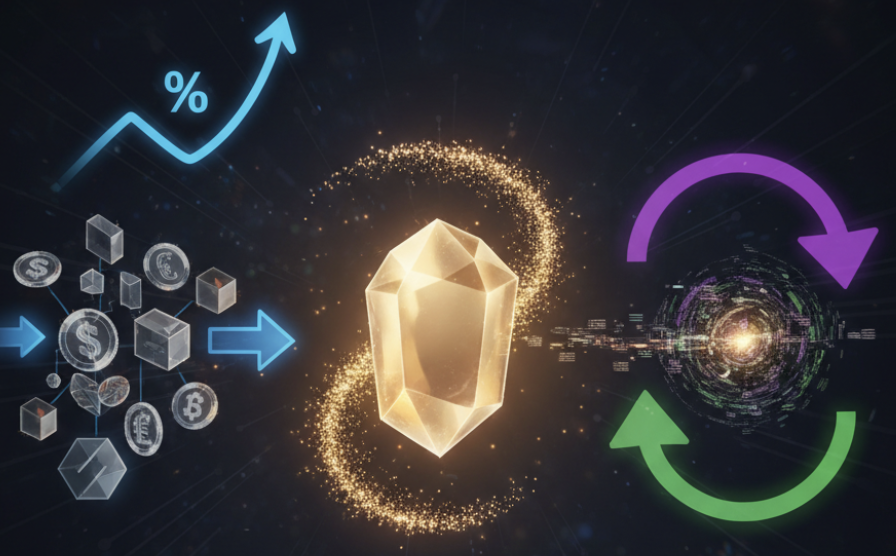
このプロジェクトの主なサービスは次の2つです。
- レンディング(貸出):保有する仮想通貨をプロジェクトに貸し出し、年利(最大12%など)を得る
- スワップ:通貨同士の交換時の手数料・差益を配当として還元
これらを組み合わせて「預けているだけで複利的に増える」よう見せています。
ただし、表示されている利回りは過去実績なのかプロモーションなのか
明示されていない点が大きな不安点です。
利回りの原資とリスクの裏側
説明資料では、運用先を OTC/DEX市場 や 流動性プール取引 と謳っています。
つまり、レンディング先が“プロジェクト自身”であったり
流動性を提供するプールであったりするというモデルが想定されており
利用者が直接借り手を選べるわけではありません。
これは事実上、運用委託に近い構造といえます。
運用自体がプロジェクト内部に集中している場合、プロジェクトに技術的・資金的問題が起きれば、預けている人すべてに影響が及ぶリスクがあります。
“DeFi”を掲げながら中央集権的な実態
IZAKA-YA は「分散型金融(DeFi)」をアピールしますが
以下の点から“分散性”を担保できているかは疑問です。
- ガバナンストークン(利用者が運営に影響を与える権利)が確認できない
- 保有アドレス数に偏りがあり、資産の集中が見られるという指摘
- 運営側が流動性や貸出条件を随時変動できる体制が示唆されている
これらは、表面的なDeFiの名のもとに中央集権的運用が含まれている可能性を示唆しています。
規制と法的保護の不在
運営会社は香港拠点とされていますが、利用規約にはケイマン諸島の準拠法という記述もあり
法的な拠点が複数にまたがっている印象を受けます。
こうした構造は、トラブルが起きた時の法的救済を難しくします。
国内登録もないため、日本国内での投資家保護措置は適用範囲外となります。
数字の可視性と信頼性
アプリや管理画面には残高や利回りの表示があります。
しかし、これがブロックチェーン上で裏付けられているかどうかは明示されておらず
オフチェーンで数値を操作できる可能性があります。
レンディング/貸出系のプロジェクトで最も重要なのは、
預けた資産が“本当にどこにあるか・誰が運用しているか”が可視化されていること。
それが曖昧なままでは、数字を信じる根拠になりません。
メリットも理解しておきたい

もちろん、IZAKA-YA に「使える面」もあります。
- 保有しているだけで利息を得る仕組みは敷居が低い
- 通貨ペアの種類やキャンペーンによって選択肢が豊富
- KYC不要など簡易スタートの設計がされていることもある
ただし、メリットを追うなら
その裏にあるリスクの合理性を理解したうえで使うことが絶対条件になります。
実践するなら“リスク制御重視”で
もし使ってみるなら、僕は次の手順を取ります。
- 少額資金で“預け→利息→出金”の往復テストを先にやる
- 利回りや残高はブロックチェーンで可視化できるか確認
- 複利設定・自動再投資はオフから始め、挙動を把握できてから有効にする
- キャンペーン狙いは“もらって離脱”の短期視点で使う
こうして、「信じるに足るなら少しずつ」「不信感あればすぐ撤退」を原則に動きます。
私の結論
IZAKA-YA は「預けて増える可能性」を示しているけれど
それを100%保証する仕組みではありません。
透明性・規制・可視性のいずれかが曖昧であり、リスクを無視するべきではない事案だと私は判断します。
副業も投資も、安易な“楽して儲かる”を求めるほど遠回りになります。
僕が選ぶ道は、まず「小さく確かめること」--それが結果につながる確率を少しでも上げる方法だと思います。









